連載/インタビュー記事
「音の信号処理」が生み出す社会的な貢献 - フジサンケイビジネスアイ「Bizクリニック」(全15回、2020年)

筆者プロフィール
エヴィクサー 代表取締役社長 瀧川 淳
たきがわ・あつし 一橋大商卒。2004年にITスタートアップのエヴィクサーを設立し現職。08年以降、デジタルコンテンツ流通の隆盛をにらみ、他社に先駆けて自動コンテンツ認識(ACR)技術、音響通信技術を開発。
テレビ、映画、舞台、防災などの分野へ応用し、「スマホアプリを使ったバリアフリー上映」「字幕メガネ」を定着させる。1979年生。奈良県出身。
連載15回分の記事については、連載記事をまとめた小冊子(PDF)、英語翻訳版を下記にご用意しております。
→ 連載記事をまとめた小冊子PDF
→ 英語翻訳版はこちら
第1回 音の信号処理が「字幕メガネ」に (2020年4月7日掲載、4月11日Yahoo!ニュース転載)
フジサンケイビジネスアイ 2020年(令和2年)4月7日付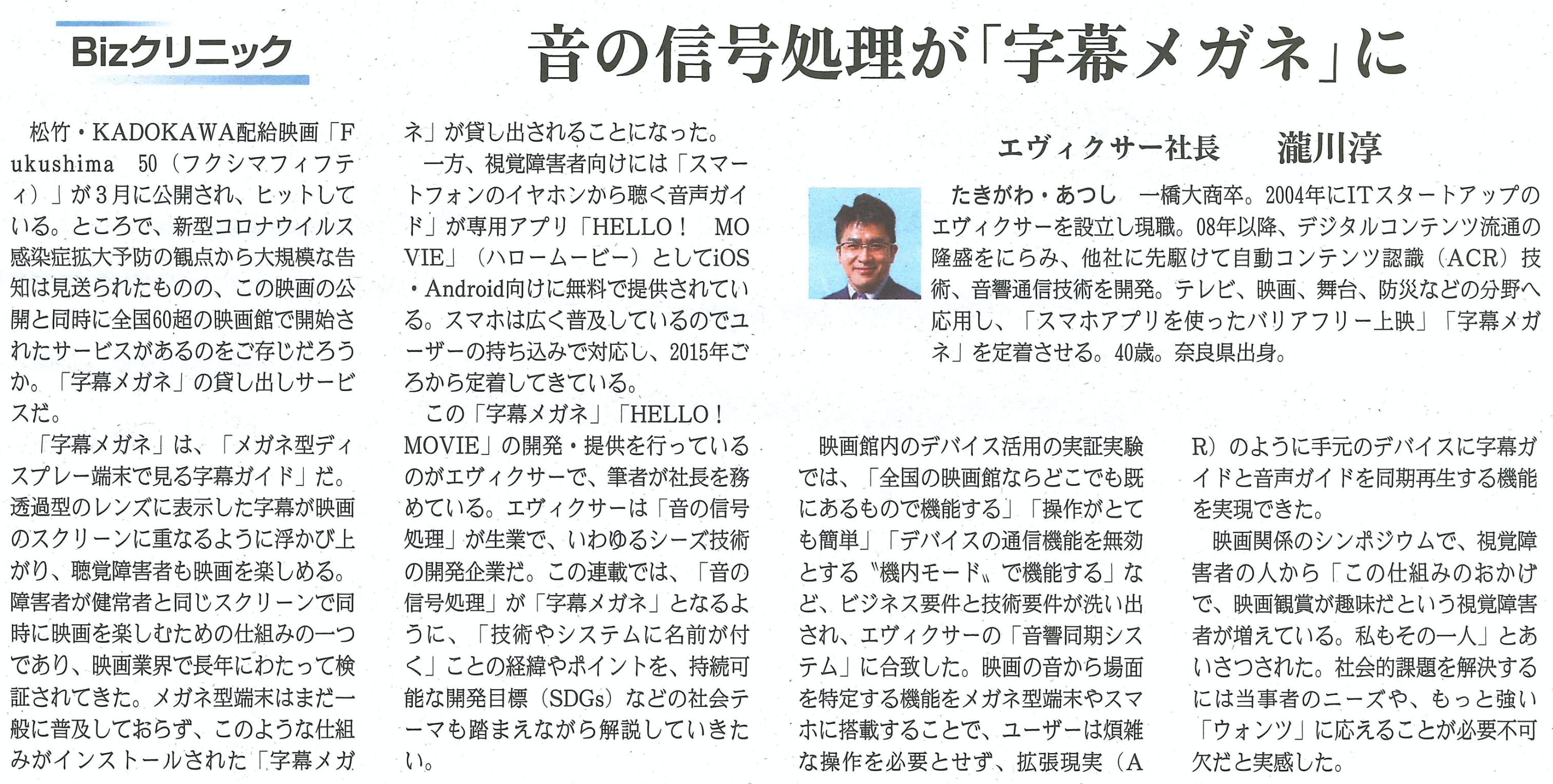
第2回 「勝ちにも不思議の勝ちはない」 汎用技術は採用必然性の積み重ね (2020年4月14日掲載、4月18日Yahoo!ニュース転載)
フジサンケイビジネスアイ 2020年(令和2年)4月14日付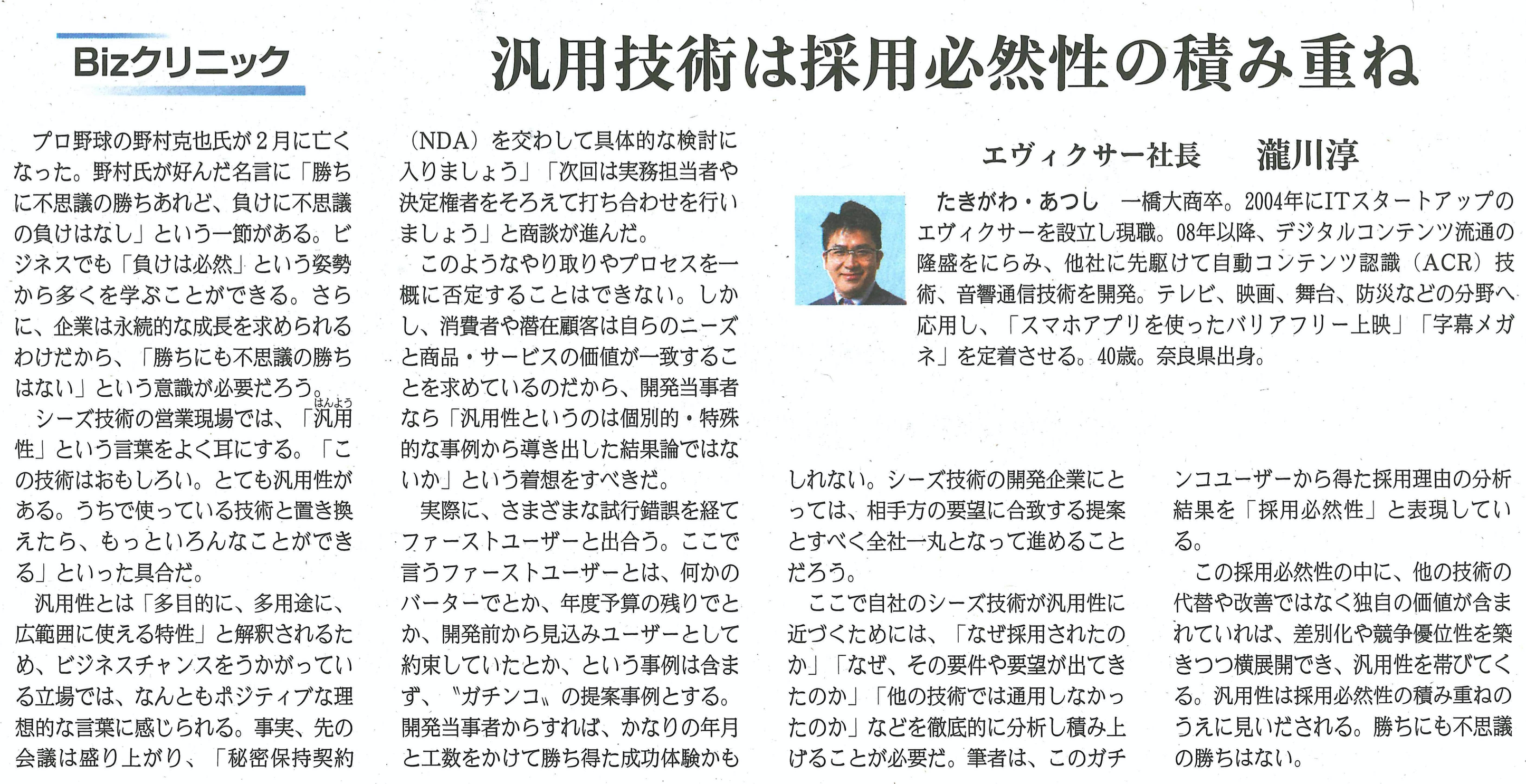
第3回 アフターコロナへ 自社技術デビューの鍵はトレンド把握 (2020年4月30日掲載、5月7日Yahoo!ニュース転載)
フジサンケイビジネスアイ 2020年(令和2年)4月30日付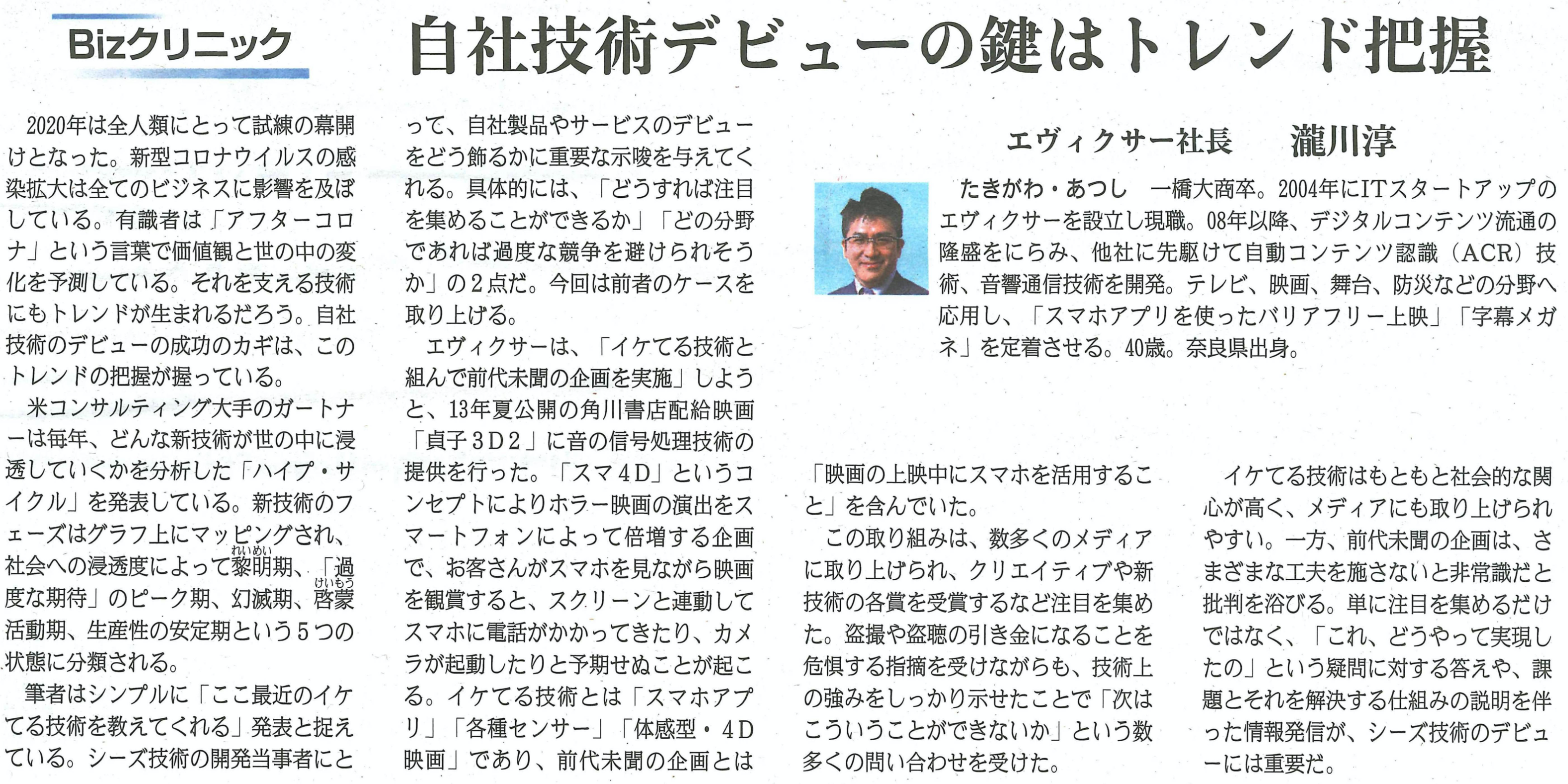
第4回 技術ブランディングは急がず育てるのが望ましい (2020年5月12日掲載、5月18日Yahoo!ニュース転載)
フジサンケイビジネスアイ 2020年(令和2年)5月12日付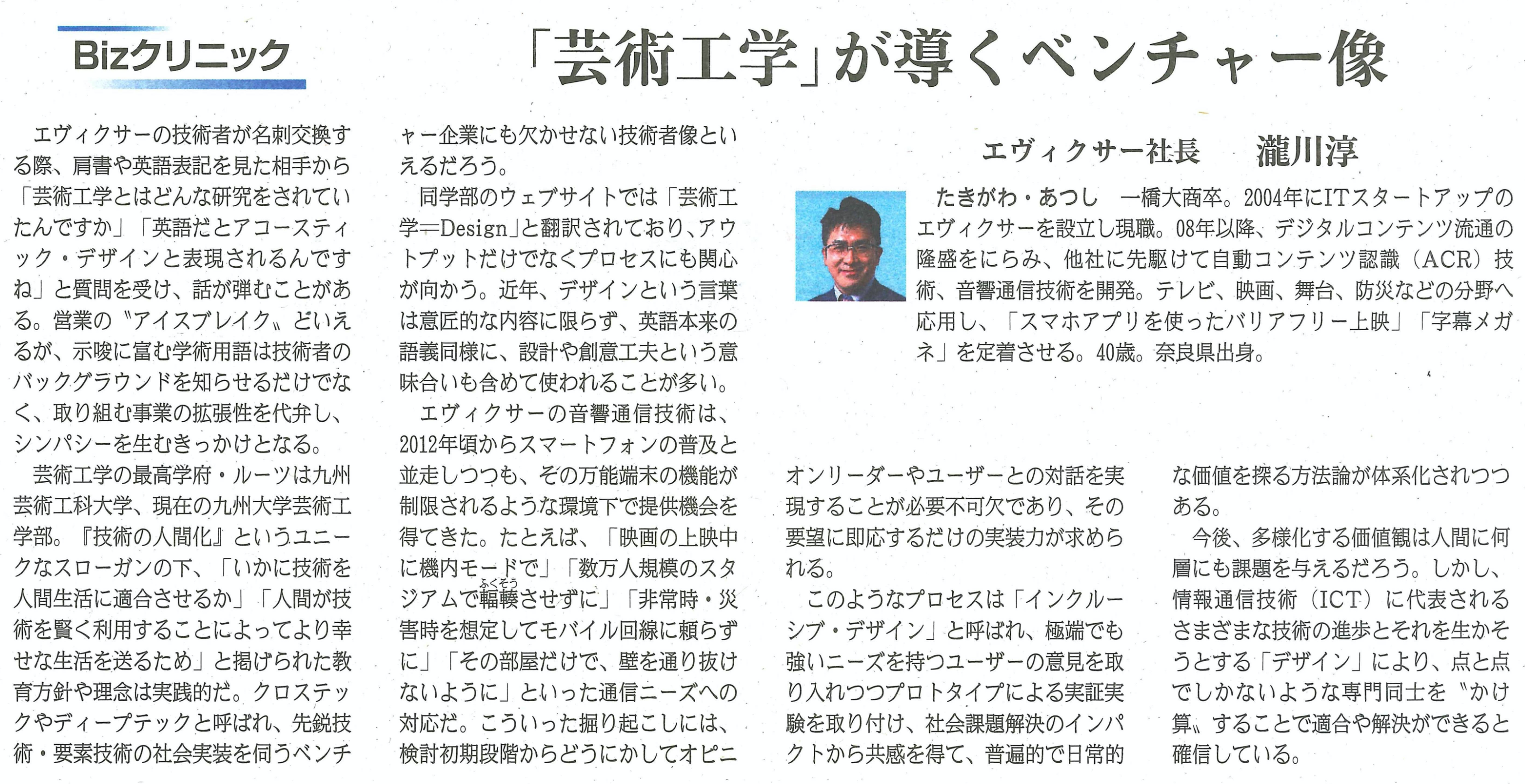
第5回 重要な「アクセシビリティ」という考え方 (2020年5月19日掲載、5月24日Yahoo!ニュース転載)
フジサンケイビジネスアイ 2020年(令和2年)5月19日付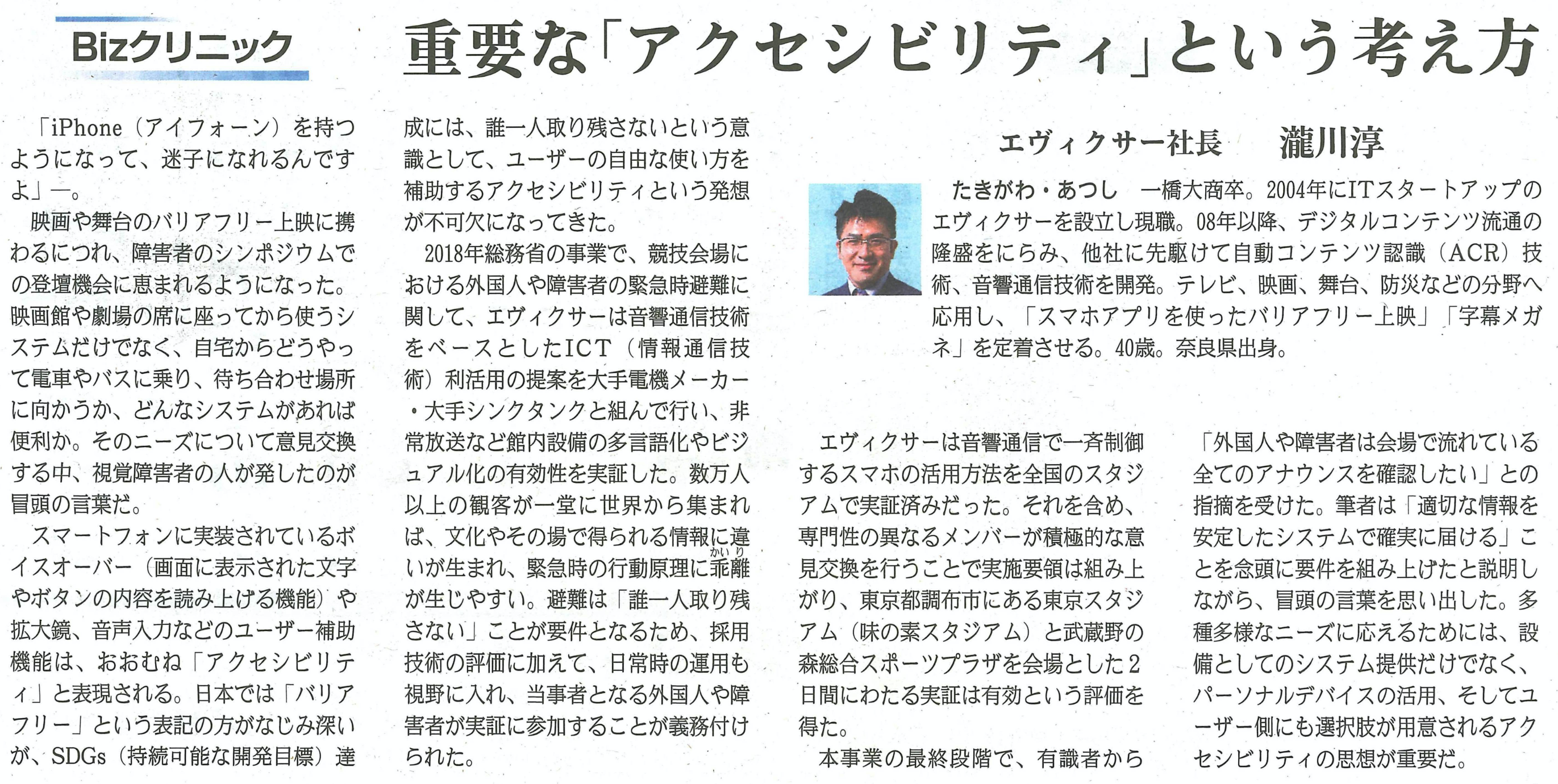
第6回 オープンイノベーションへ助成活用 (2020年5月26日掲載、5月30日Yahoo!ニュース転載)
フジサンケイビジネスアイ 2020年(令和2年)5月26日付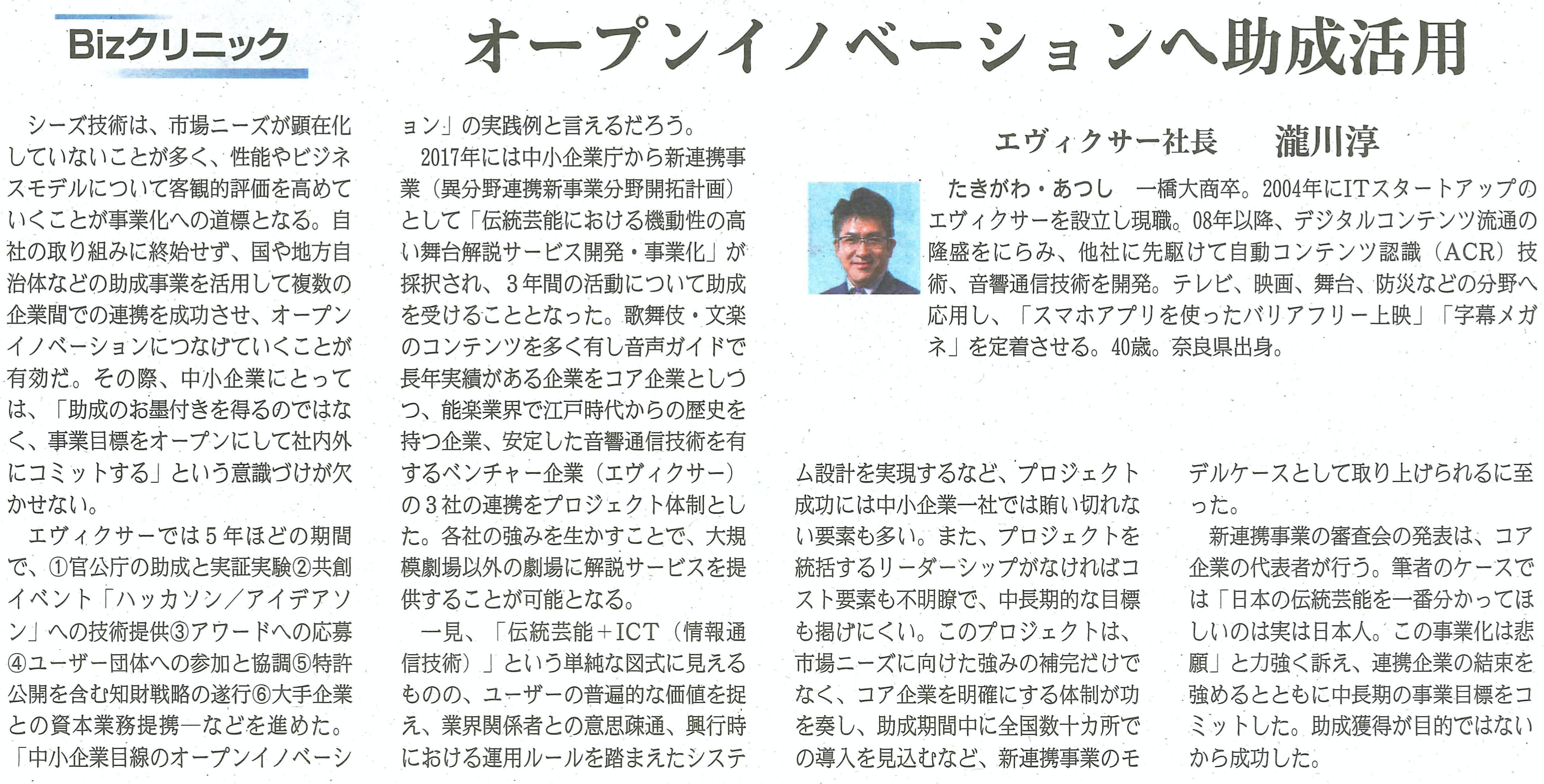
第7回 アワードに挑み開発ストーリー打ち出す (2020年6月2日掲載、6月6日Yahoo!ニュース転載)
フジサンケイビジネスアイ 2020年(令和2年)6月2日付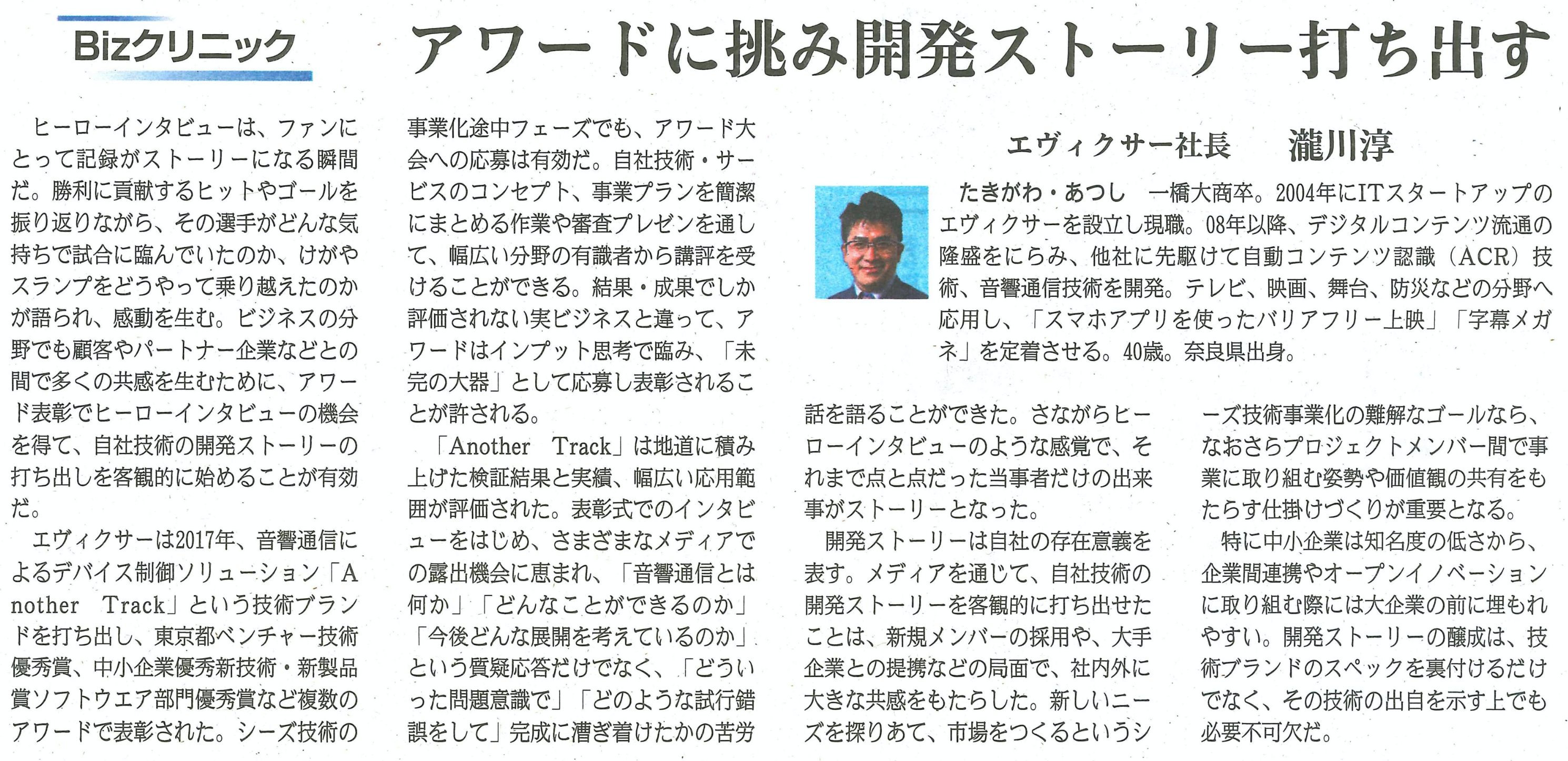
第8回 企業提携の間を埋める「味わい深い」商人の心得 (2020年6月9日掲載、6月13日Yahoo!ニュース転載)
フジサンケイビジネスアイ 2020年(令和2年)6月9日付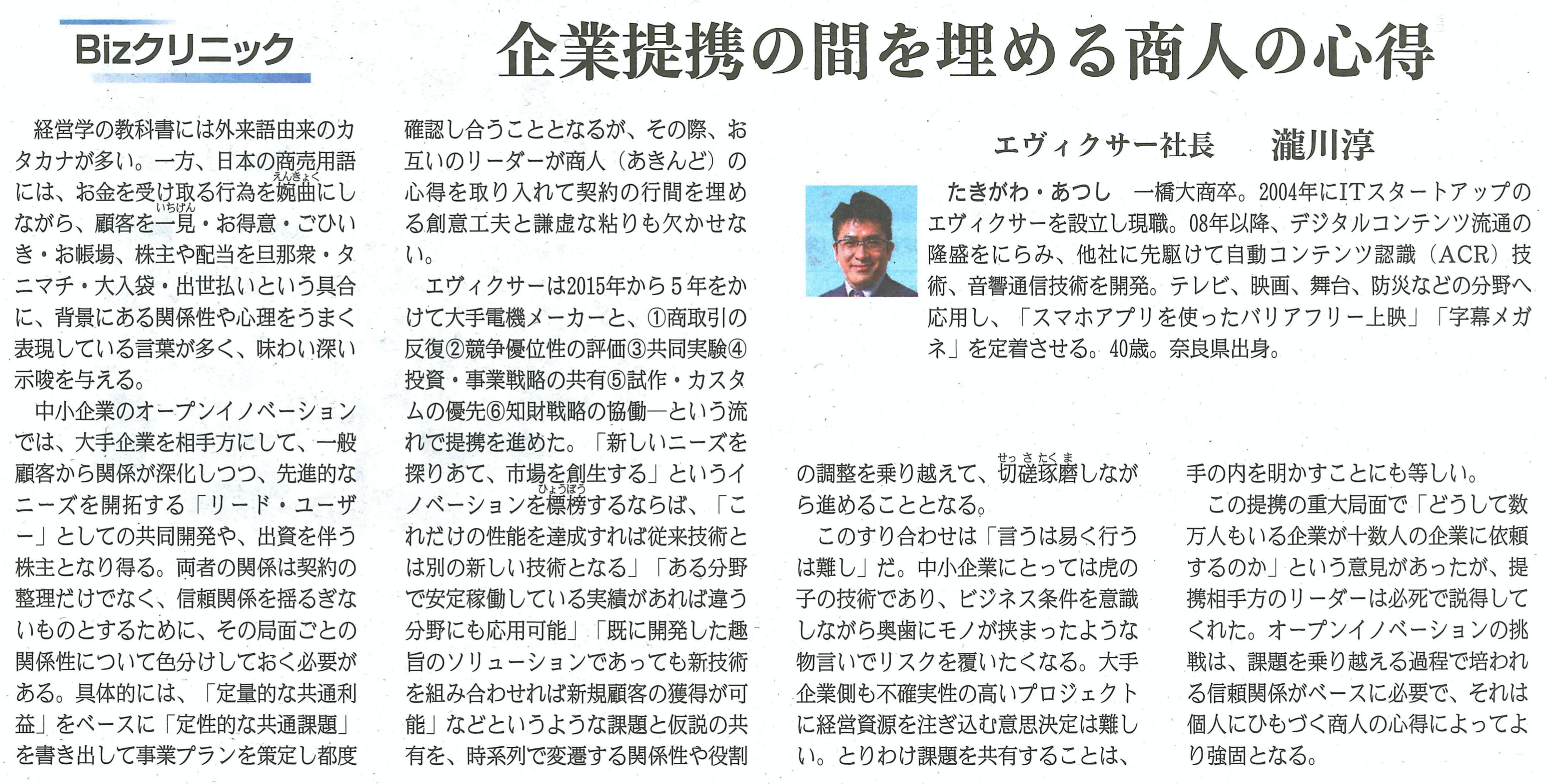
第9回 技術者と「同じ釜の飯を食う」楽しさ (2020年6月16日掲載、6月21日Yahoo!ニュース転載)
フジサンケイビジネスアイ 2020年(令和2年)6月16日付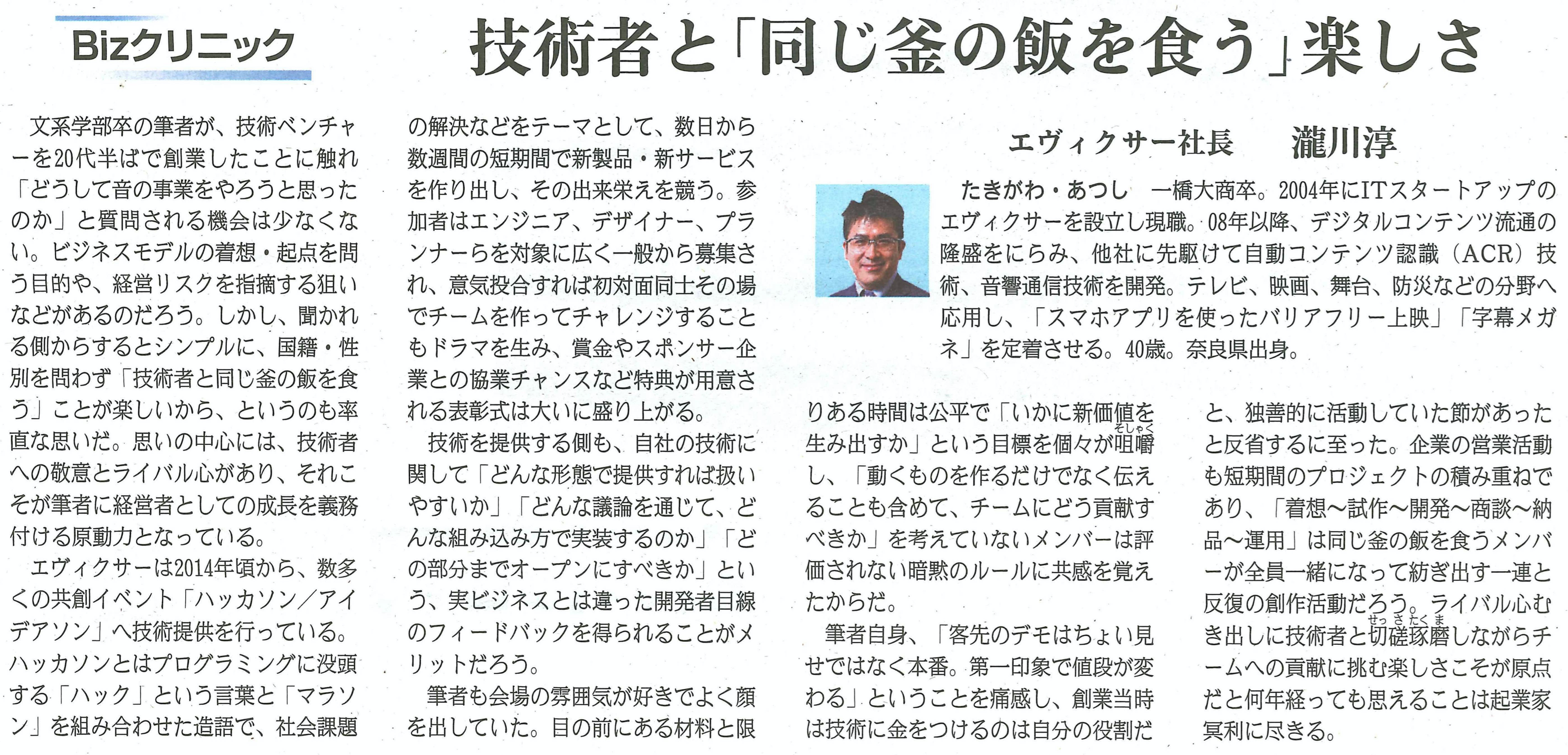
第10回 アフターコロナ 共感生む競争優位性が鍵 (2020年6月23日掲載、6月27日Yahoo!ニュース転載)
フジサンケイビジネスアイ 2020年(令和2年)6月23日付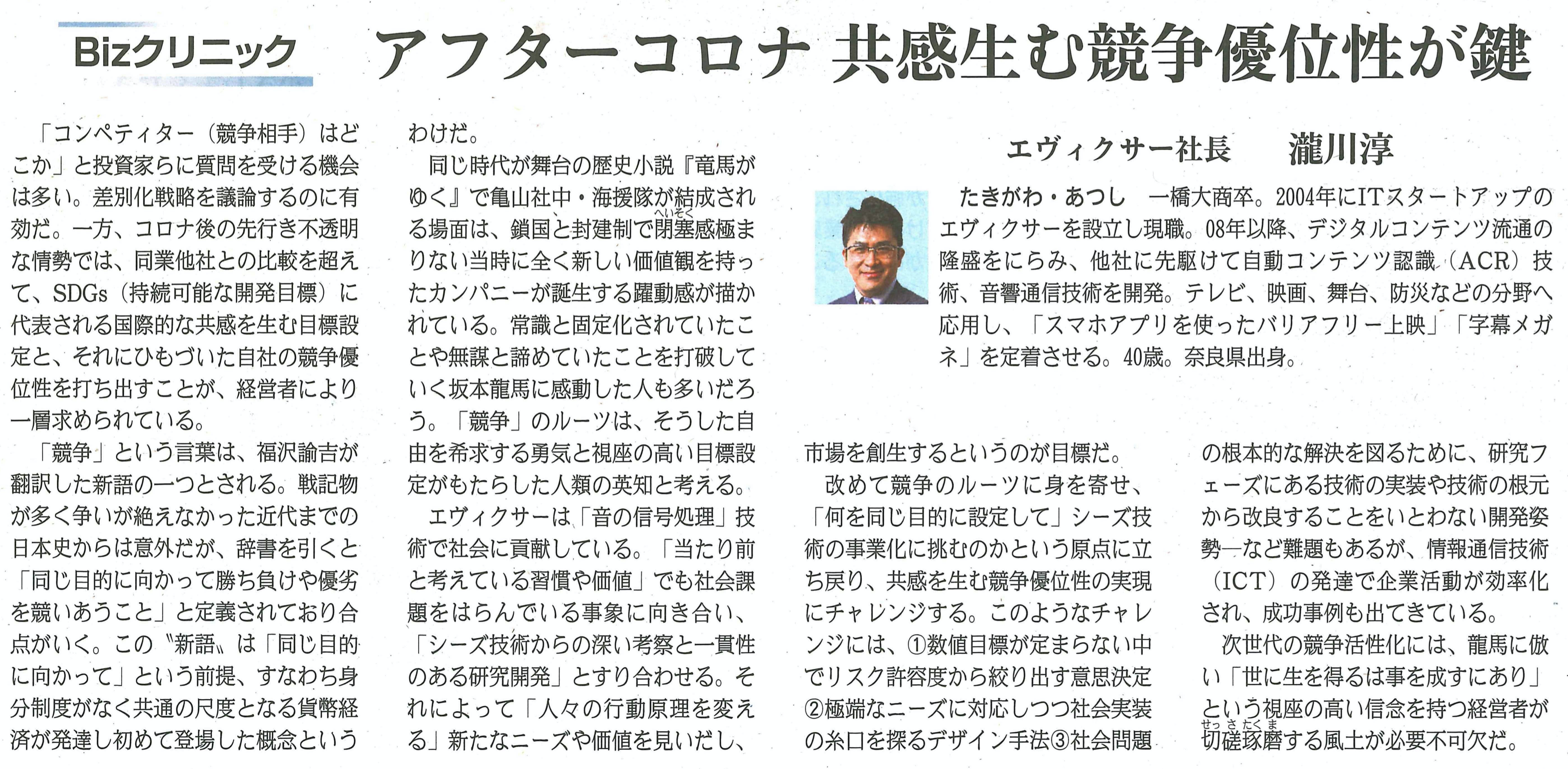
第11回 経営者自身も“ウェルビーイング” (2020年6月30日掲載、7月5日Yahoo!ニュース転載)
フジサンケイビジネスアイ 2020年(令和2年)6月30日付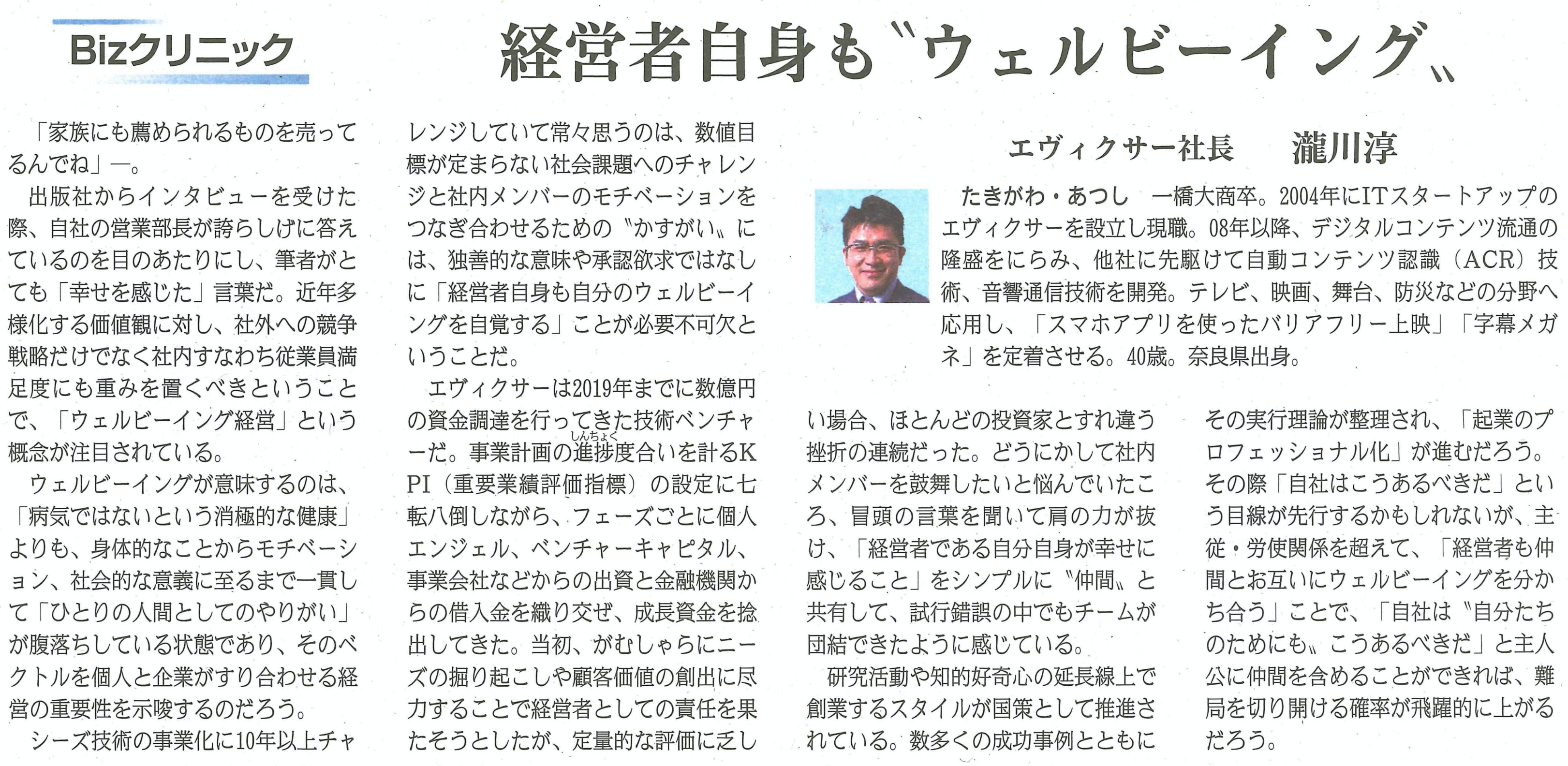
第12回 “聞こえない音”の最新技術は10年越し (2020年7月7日掲載、7月12日Yahoo!ニュース転載)
フジサンケイビジネスアイ 2020年(令和2年)7月7日付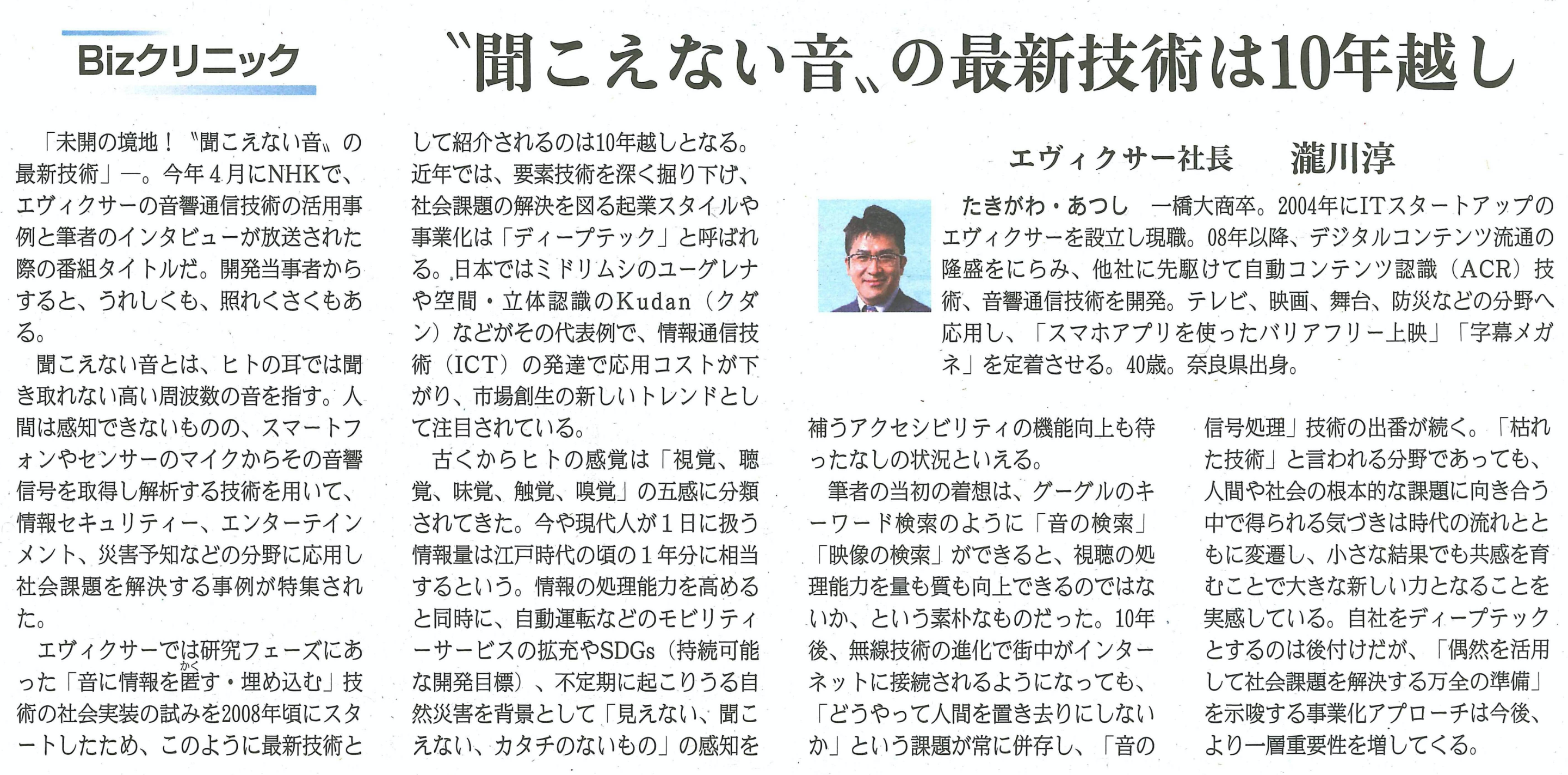
第13回 災害時に「今+その場所」へ意思伝達 (2020年7月14日掲載)
フジサンケイビジネスアイ 2020年(令和2年)7月14日付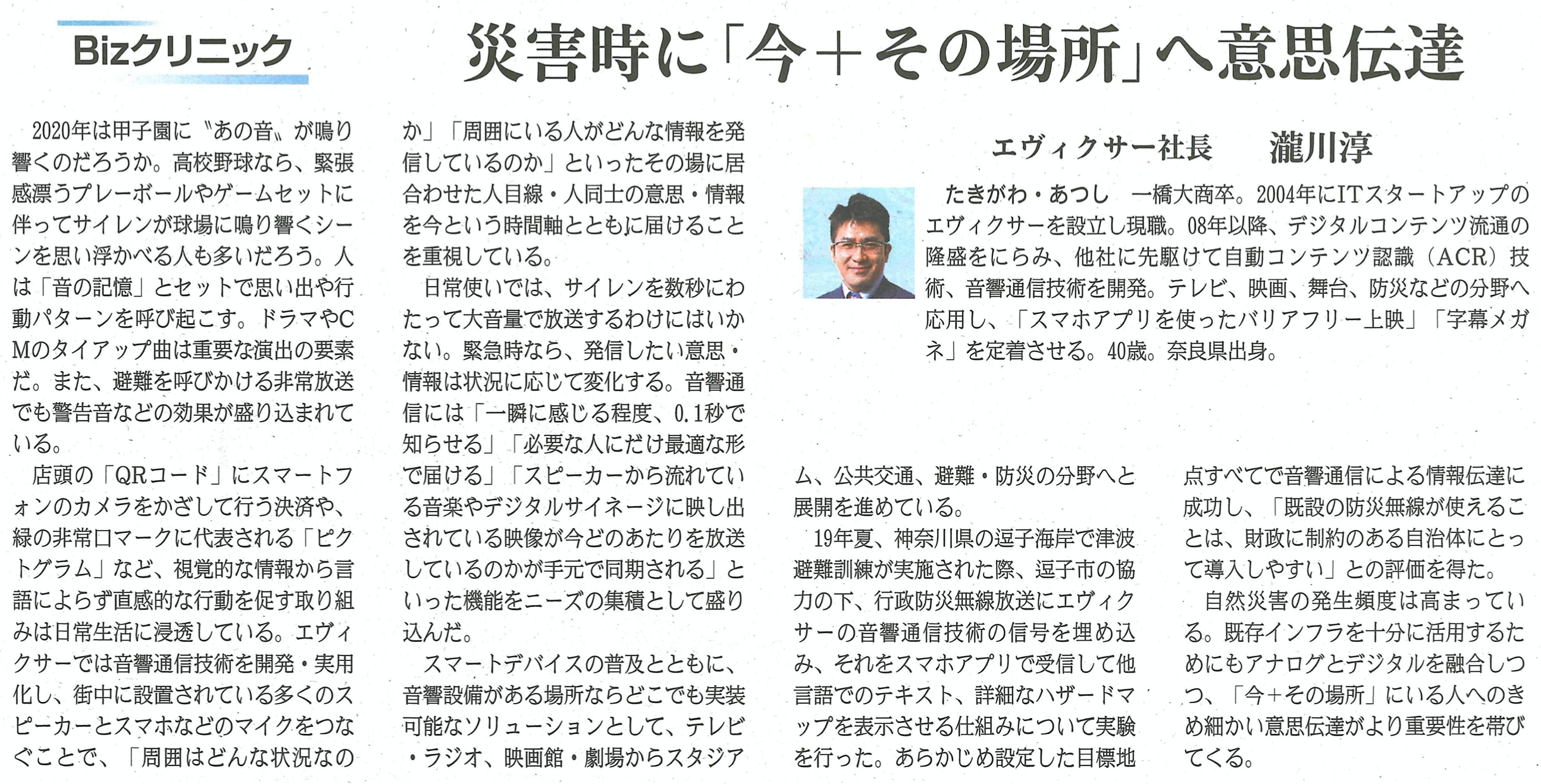
第14回 「芸術工学」が導くベンチャー像 (2020年7月21日掲載、7月26日Yahoo!ニュース転載)
フジサンケイビジネスアイ 2020年(令和2年)7月21日付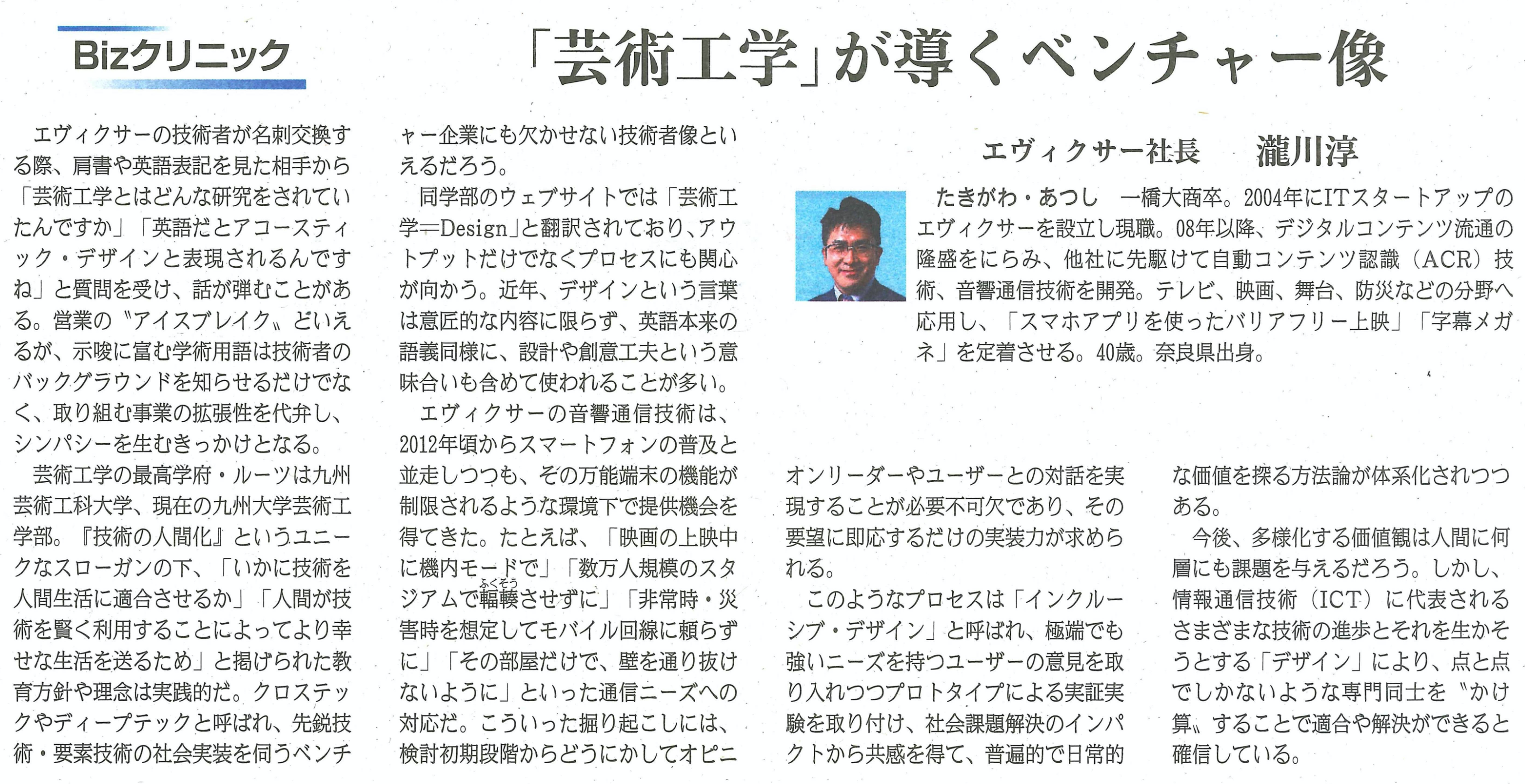
第15回 「音で見える つながる 楽しむ」世界を (2020年7月28日掲載、8月1日Yahoo!ニュース転載)
フジサンケイビジネスアイ 2020年(令和2年)7月28日付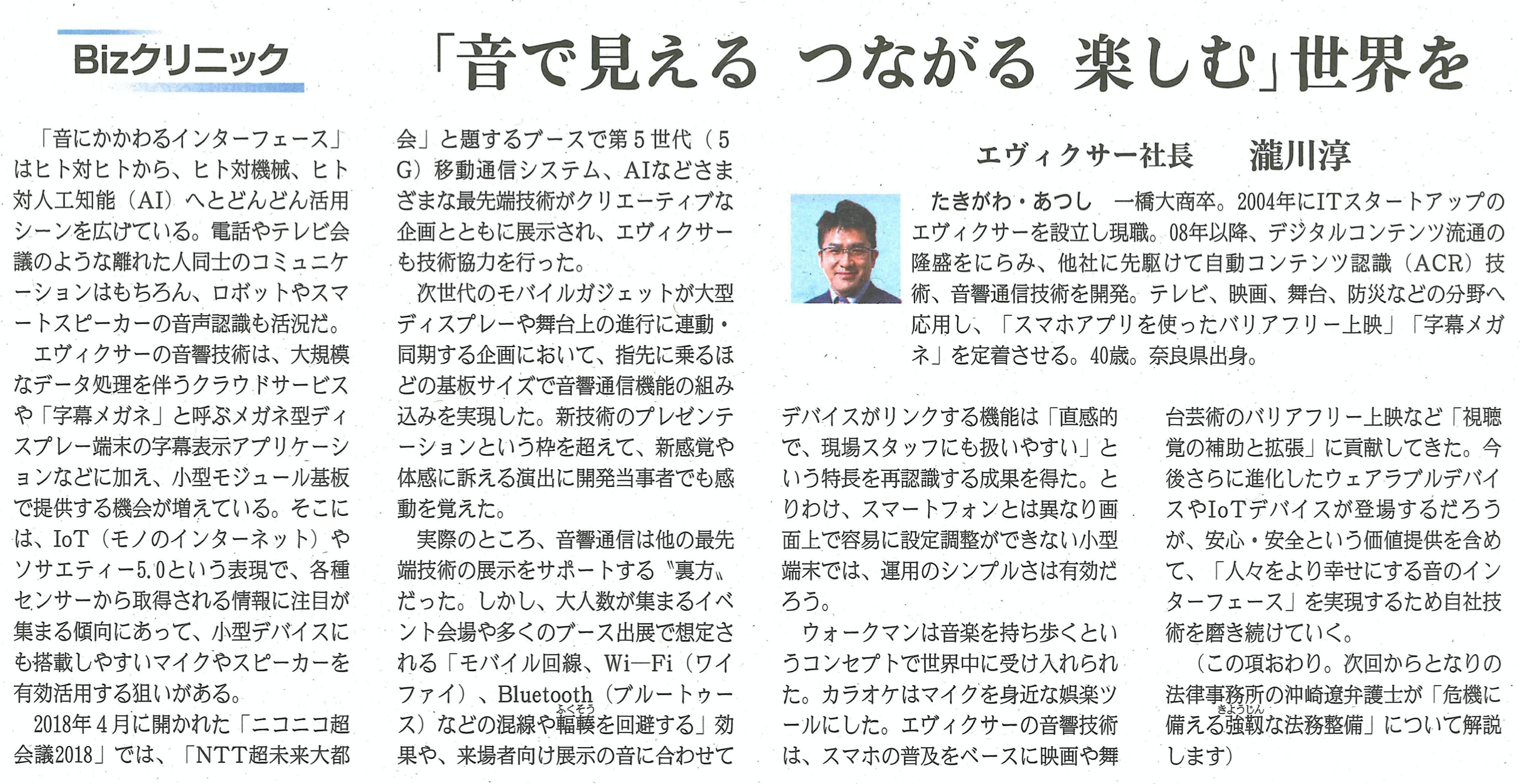
「自分を活かす会社でイキイキ働こう! -魅力的な中小企業探しのすゝめ-」 (監修/八木田鶴子、編集/合同会社みんプロ、2019年)
第7章 音で人と人とをつなぐことに挑む – エヴィクサー株式会社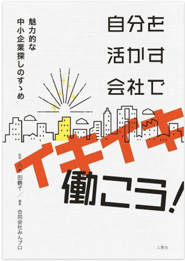
→ 書籍出版社の紹介ページ (外部サイトへのリンク)
The Urban Folks – Technology 「シーズ志向で市場の創生を目指す」 (2018年)
筆者プロフィール
技術ベンチャー創業経営者 エヴィクサー株式会社 代表取締役社長 瀧川 淳
2004年3月、エヴィクサー株式会社を設立。2008年ころより、業界に先駆けてACR(自動コンテンツ認識)技術、音響通信技術を開発し、テレビ放送局、大手広告代理店、映画会社、舞台のセカンドスクリーン、O2Oの取り組みで数多くの実績をもつ。要素技術の事業化、シーズオリエンテッドのビジネスモデルをテーマとした講演多数。2017年に第29回「中小企業優秀新技術・新製品賞」ソフトウエア部門で優秀賞、「MCPC award 2017」サービス&ソリューション部門で特別賞、「2017年 世界発信コンペティション」製品・技術(ベンチャー技術)部門で東京都ベンチャー技術優秀賞を受賞。2003年3月、一橋大学商学部卒。2017年より一般社団法人日本開発工学会理事を務める。
第1回 2018年5月6日 「死の谷とハイプ・サイクル」
第2回 2018年6月8日 「開発者目線とユーザー目線の使い分け、ブランディングの開始時期」
企業診断「シリーズ 挑戦する経営者」 (2017年)
経営者プロフィール
エヴィクサー株式会社 代表取締役社長 瀧川 淳
一橋大学在学中、東京電力の社内ベンチャー企業で長期インターンシップ・契約社員を経験。卒業後、韓国ベンチャーの日本法人立ち上げに参画。その後、MBOで独立し、エヴィクサー株式会社の代表取締役社長に就任。音響技術をベースとするシードで、新たな市場づくりに挑戦中。